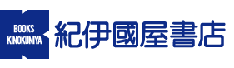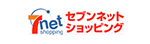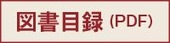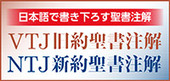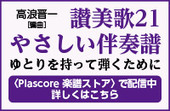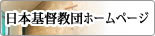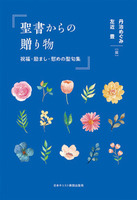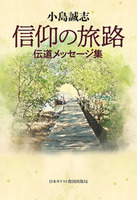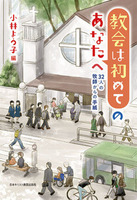-
2023.09.20
-
2021.08.02
深い淵から
希望と慰めのみことば

すべてのことは神の統治のもとにあると信じながらも、納得できないことが私たちを襲う。しかし、編者は告げる。それでも神は正しく恵み深い、と。50年に及ぶ牧会生活の中から書き留められた、苦難、悲しみ、孤独、災害など「深い淵」のただ中で聴き、祈るための主の御言葉集。
【編者紹介】今橋 朗(いまはし・あきら)
1932年、東京に生まれる。慶應義塾大学卒業。東京神学大学大学院修士課程修了。米国ギャレット神学校留学(キリスト教教育、礼拝学)。日本基督教団蒔田教会牧師、日本聖書神学校校長、キリスト教カウンセリングセンター理事長を歴任。2014年逝去。
【まえがきより】
「主よ、わたしの叫びが御前に届きますように。
御言葉をあるがままに理解させてください。」
(詩編119編169節)
この被造世界には、さまざまな悲しみや不条理と思わざるを得ないことが絶えず存在する。すべては神の統治のもとにあると信じていながら、それでも納得できないこと、納得したくないことが起こる。神はそれでも正しいのだろうか? そうだ、それでも神は正しく、恵み深い!
若い日に神に召されたと信じて牧師の道を歩み始めてから半世紀が過ぎた。遣わされた教会内外で、実に多くの人々と出会い、多くの悲しみと出会った。そのような場合の牧会的対話において、私に求められていたのは、「牧師であること」だった。誰がその任に耐え得ようか。常識的な善意や同情、体験の中から徐々に蓄積してきた人生論的な知識や共感、牧会学の原則や牧会カウンセリングのスキルも、もちろん役に立つはずであった。しかし、私の場合、そうした「深い淵」状況(詩編130・1)のただ中にある人々の訴えを聞き、牧会的対話と共感と祈りへと導かれていくために、どうしても必要だったのは、まず自らの内に、神の言葉を聞くことであった。そうでなければ、この重い現実に立ちすくみ、圧倒されてしまったであろう。「助言が多すぎて、お前は弱ってしまった」(イザヤ書47・13)。
もちろん、その日の面談者がどのような状況の中で、どのような気持になり、牧師を訪ねたいと思ったのか、具体的な事情は前もって分からない。したがって、その人の状況と状態にとって的確な聖句を探し出すのではなく、自分自身の中に御声を聞きつつ、その人の語る情報を受けとめるための聖句である。その人に読み聞かせたり、教えたり、あるいは手紙やカードに記して贈るのが第一目的ではない。まず自らが御言葉を聞き、御言葉に頼りつつ訴えに耳を傾け、御言葉を根拠にして共に祈るためである。「主よ、あなたはこうおっしゃっておられるではありませんか……」と。すなわち、「牧師」として関わるためである。それは教師・助言者・援助者・回答者、まして解決者とは異なる使命であろう。
長い牧会生活の間、毎週木曜日を牧師面談日にしてきたが、平均して一日、二〜三人の教会員・求道者・その他の方々が訪れてきた。わざわざ予約をとって多忙の中来訪するのであるから、かなり深刻な事態の中にいる人々であった。さらにある時期(十年間ほど)、月に一度「祷告の集い」という集会を続けていた。日曜日の諸集会が終わったあと、夕刻の礼拝堂に集まる。それはオープンな集会ではなく、教会に祈ってもらいたい問題や課題をもっている人々だけの集いである。定刻、聖壇の前に座席を整えて副牧師と共に待っている。多くても数名、ある時は誰も来ない日もある。
そこで述べられた個人的な情報には守秘義務があることを確認し、問題をシェアする。確認のための質問をすることがあっても、コメントは一切しない。そして、このような私たちに呼び掛けてくださる御言葉をいくつか読んで、導かれるままに祈った。神からの言葉を聞くことなくして祈る祈りは、往々にして自己主張や願望や独語になりやすいし、さらには、困難な状況の中におかれたときには、聖書を開く余裕や気力もおとろえることが多い。第一、聖書の中のどこを読めばよいのか思い付くことさえ難しい。結局、祈りとは「気の持ちよう」の問題だと思われてしまうかもしれない。祈りとは神との「対話」なのである。このようにして、信仰と慰めと希望と平和を告げ、語りかける小さい聖句が、長年のうちにたくさん溜まった。(当然のことながら、しばしば繰り返し引用されるものとそれほどではない聖句の差はある。)機会があってこれらを集めてみた。まるで貴重な小さい「落ち穂」を拾い集めるように……。
聖書の中から特定の一句、または数個の聖句を、このようにそのコンテキストから切り離して取り出し、このように用いることについて問題があり、批判があることはよく理解している。しかし、聖書の御言葉は、聖書学的、歴史的、文献学的、教義学的、典礼的、教育的、あるいは文学的に解釈され理解され用いられるにとどまらない。神の臨在はその御言葉において具体化され、御許から発信された恵みと力であり、天からの御使いとしてここに来臨する。まさに「主は御言葉を遣わして彼らを癒し 破滅から彼らを救い出された」(詩編107・20)。この場合、聖句自らが恵みの偉力を発揮するコンテキストとは、それを切に必要としている(双方の)人間の状況であり、祈ろうとしている信仰なのである。したがって、聖句はまず牧師の必要性のためであると先述したが、困難の中にある来訪面会者も共に聞き(読み)、これに依り頼みつつ共に祈ることができればさらによい。
これは聖句の緊急用法と言えるかもしれない。永遠の神の御言葉は緊急の御言葉でもある。「エシュルンの神のような方はほかにはない。あなたを助けるために天を駆け 力に満ちて雲に乗られる」(申命記33・26)、「主は仰せを地に遣わされる。御言葉は速やかに走る」(詩編147・15)。
しかし当然ながら、いわばこのように断片的に選び出された聖句は互いに異なる(ある場合には、矛盾した)メッセージを語ることも多い。例えばある聖句は、即座に来てくださる助けを語るが、他の聖句は静かに忍耐して待つことが祝福となることを告げる。単一の特定の聖句が「おみくじ」や呪文のようになってはならない。個々の状況と祈りに語りかけるある聖句のメッセージは、神の福音の全構造(創造、契約、歴史、キリストの御業と教えと生涯、死と復活、終末の希望と約束、そして教会とキリスト者の生活)との関わりの中で、この個別の緊急的状況に発せられた御言葉であることを理解し感謝して聞きとり、信じるのである。既に三百年近い歴史をもつヘルンフート兄弟団の「ローズンゲン」(日々の聖句)が、ローズング(合言葉)として任意に選ばれた日毎の旧約聖句が、神学的関連性によって新約聖書から選ばれた一句と併置され、そのメッセージに呼応して祈りやアンダハト(聖想)が記されている(ドイツ語版)という構造は、極めて重要であると言わねばならない。それは、聖書と福音の構造を示すとともに、この個人的聖書信仰が共同体のきずなとなることを現実化している。先述した牧会面談や祷告の集いで「ローズンゲン」がどれほど有効であったかは驚くほかない。
ここに溜まった「短い聖句」集は、実践の結果であって、意図と企画によって編集された著作ではない。状況に対して呼び掛けてくる神の言葉は、全聖書の中にまだまだ満ちている。それらと出会い、共有し、御言葉そのものがどのように働いてくださるかを知り、神に感謝したい。しかし考えてみれば、この種の聖句や賛美歌の「落ち穂」コレクションは、多くの(あるいはほとんどすべての)牧師や信徒ひとりびとりが、人知れず行っていることではないのか。そう考えると、本書の刊行は改めて恥ずかしいことではないのか。
「というのは、神の言葉は生きており、力を発揮する」からである(ヘブライ人への手紙4・12)。
本書を開く前に
罪の告白と赦し
苦難・恐れ
不安・悲しみ・孤独
病気・災害
死
平和の祝福
あとがき